秋になると紅葉の見頃予想や人気スポットなどの特集が旅行雑誌やテレビ番組で組まれたりしますよね。今回は、この紅葉のメカニズムについてシェアします。
寒くなると葉が紅葉する理由
紅葉のきっかけは、植物が葉に栄養供給することを停止してしまうから。葉への栄養供給が停止されると、葉は光合成のための組織であるクロロフィル( 葉緑素)の分解を始めます。
植物の葉が緑色なのは、このクロロフィルが存在するからなんです。クロロフィルの分解が進むにつれて、葉から緑色が失わ れていきます。

植物が葉を持つ最大の理由は光合成で栄養を得るため。北半球の国では夏至を頂点として徐々に日照時間が短くなっていきます。秋になると、かなり早い時間に日が暮れて驚くこともありますよね。
日照時間が短く、気温も下がってくると光合成の効率も低下していきます。葉を維持することにも栄養が必要です。
冬に向けてどんどん光合成で得られる栄養は低下していき、葉を維持することが植物の負担になってきます。
最終的に光合成のコストパフォーマンスはかなり悪くなり、葉を捨てて休眠に入る決断をします。植物が休眠の決断をする時期は、日中の気温が8度になる頃です。

寒くなると動物が冬眠するように、植物も眠りに入るんです。
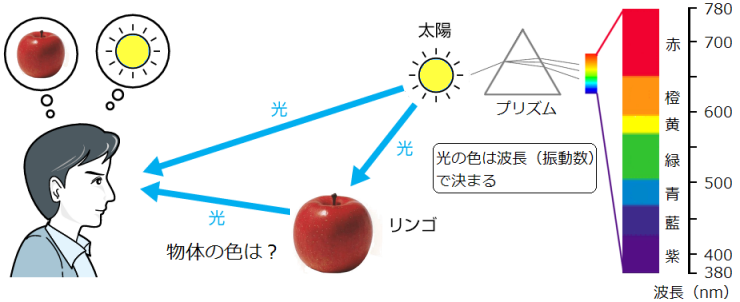

黄色に染まる葉と赤く染まる葉の違い
紅葉には大きく分けてなどの赤色に染まる葉と、黄色がありますよね。一般的にどちらも「紅葉」と呼ばれることが多いですが、狭義には葉が赤く染まる現象を「紅葉」、黄色に染まる現象を「黄葉」と定義されています。
幹からの栄養供給が止められ、クロロフィル(葉緑素)も吸い上げられてしまった葉は緑色を失っていきます。
すると今まで緑色に隠れていた黄色の成分(カロチノイド)が私たちの目で認識できるようになります。これが葉が黄色に染まる仕組みです。
黄色く染まる植物で最も有名なのは銀杏(イチョウ)ではないでしょうか。大阪市内では街路樹に利用されている場所も多いです。他にもシラカバが有名 どころですね。
幹からの栄養供給が止められた後も葉は光合成を続けます。その結果、微量ながら枝に運ばれれない糖分が葉の中に溜まってしまいます。
この糖分の量が葉を赤く染めるポイントになるんです。 葉に溜まった糖分は、葉の中にあるクロロフィル(葉緑素)と化学反応を起こしアントシアニンに変化します。このアントシアニンが葉を赤に染める色素になるんです。
こちらは、カエデ、ナナカマドなどが代表的な植物ですね。

綺麗な紅葉になるための条件
毎年同じように見える紅葉ですが、いつもより綺麗に見えたり、逆に残念に見えたりした経験はありませんか。綺麗に葉が色を変えるには3つの条件がある んです。この3つの条件によって紅葉の出来が変わってきます。
秋になって日照時間が短くなるのですが、そんな中でも葉が日に当たる時間を確保できることが綺麗な紅葉を生む条件の1つです。
赤い色素になるアントシアニンは日光の刺激によって合成されます。曇った日が続くとアントシアニンの合成が十分に行われず綺麗な紅葉にならないこともあるんです。
葉が乾燥しすぎないためにも適度な水分が必要です。湖畔や滝の近く、河辺などに綺麗な紅葉が多いのは、地中や空気中に適度な水分があって葉が良いコンディションを保ったまま、紅葉の準備が進められるからなんです。
水辺ではない場所でも寒暖差で露が発生したり、雨が降ったり湿度が保たれることで綺麗な紅葉した葉を見せてくれます。 乾燥しすぎると綺麗に紅葉する前に葉が枯れてしまうんです。
平地では難しい昼夜の寒暖差。この気温の変化が葉をより綺麗に紅葉させます。紅葉の綺麗なスポットとして、山間部や盆地などが名を上げられるのも、寒暖差が生まれやすい環境にあるからこそなんです。



